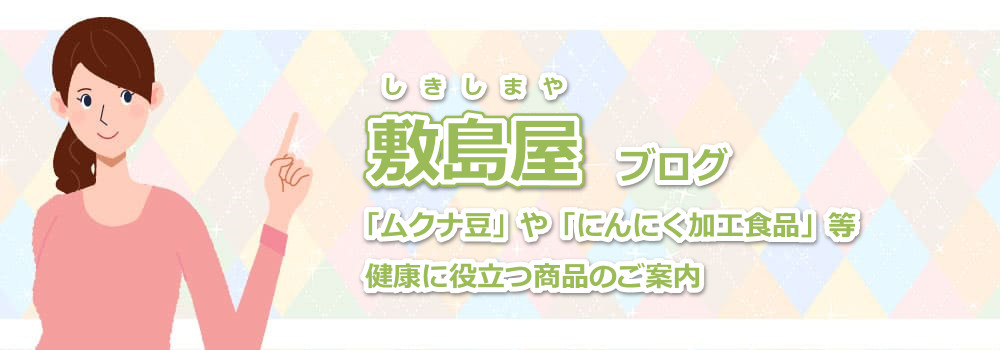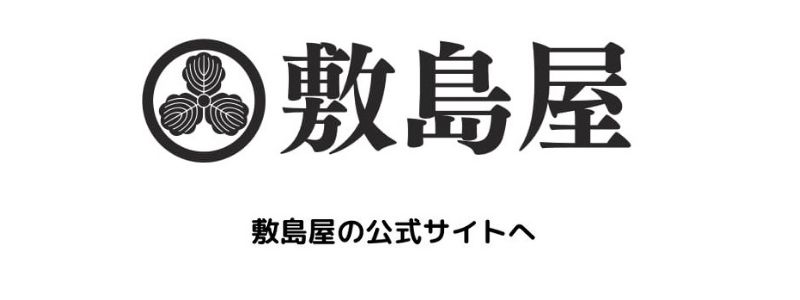八升豆解体新書 其の二
こんにちは。
敷島屋のまめ子です。
前回からお届けしている「八升豆解体新書」。
1回目はムクナ豆の植物学的かつ農学的なお話でした。
(まだ読んでいないという方は第1回目からぜひご一読ください♪)
八升豆(ムクナ豆)解体新書【その1】
さて、2回目はムクナ豆歴史編です。
もうね、これ調べるのすんごい大変でした。
ではさっそく
ムクナ豆のエトセトラ★
大公開で~す
とんでもなく昔からムクナ豆はあった!
皆さん、「アーユルヴェーダ」って聞いたことありますか?
まめ子が最初にピンときたのはインド伝承のオイルマッサージ!!
それも大正解っ!
でも、も~っとも~~~っと奥深い歴史があるんです(#^.^#)
詳しく説明しますね。

時代は3000年前にさかのぼります。
場所はインド大陸。
ここらでは医学の始まりともされる研究が始まっていました。
とはいっても健康法や生活の知恵、「幸福な人生とは?」みたいな哲学まで幅広く網羅する考え方。
「心も体も元気で長生きしたい」という願いと希望が生み出した学問で、その中にムクナ豆が「カピカチュ(Kapikachhu)」という名前で登場します。

3000年よりもずっと前。
昔々、そのまた昔からムクナ豆を食べていたことがうかがえます。
アーユルヴェーダで知られる前から食べていたんですよね、きっと。
ちなみにカピチュは強壮剤だとか神経にいいハーブだと紹介されています。

きっと当時の人々は
「ちょっと今日しんどいわ~」
「朝起きつらいっす(-_-;)」
という理由で利用していたはず。
特に驚くべきなのは“神経にいい”と分かっていたこと。
もちろん今でもアーユルヴェーダは存在していて、ドーパミンが不足することで発症するパーキンソン病やむずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)の治療などにも用いられます。
ほかにも以下の病気や症状に対しての効果も書かれています。
- 駆虫剤(腸の虫下し)
- 赤痢
- 下痢
- 腸内発酵
- 蛇咬傷
- 性の減退
- インポテンツ
- 咳
- 結核
- インポテンツ
- リウマチによる不調
- 筋肉痛
- 不妊
- 痛風
- 糖尿病
- ガン
- 精神衰弱
科学的に証明はされていませんが、長ーい歴史の中で培われてきた経験と知識の深さを感じますよね~。
3000年前からですよっ
日本、縄文時代ですから~~~~っっ


そこにムクナ豆がハーブとして使われていることがとても興味深いんですよね~。
日本にはどう広がっていったのか気になりますっ( ゚Д゚)
日本にムクナ豆がやってきた!
インドの人たちが長寿を追求していたころ、日本はやっと“豆”に出合います。
栄養価が高く、保存もできる豆は縄文時代の人たちの大事な食糧源でした。
でも遺跡から出てきたのは大豆の仲間。
いつから日本で食べられていたかというと・・・
江戸時代の初期かな?って感じです。

いくつかの書物にムクナ豆らしき豆が登場。
「八升豆」「ゐんげんささげ」「黎豆」「狸豆」「虎豆」「天竺豆」「藤豆」「葛豆」などと記載されているものがムクナ豆ではないかといわれています。
ただし、八升豆(はっしょうまめ)という名前に注意。
今お話しているムクナ豆とは全く別の豆の八升豆が日本にはあるっていうこと。
岐阜県の飛騨・美濃伝統野菜の「千石豆」、石川県の加賀野菜の一つ「加賀つるまめ」と呼ばれる「藤豆(フジマメ、味豆、鵲豆、だら[馬鹿]豆)」も別名は「八升豆」です。

う~んややこしい。
まめ子がいろいろな本を読んで「これがムクナ豆だ!」って思ったのは1712年、大坂のお医者さんの寺島良安さんが編集した本。
中国の百科事典『三才図会』を編集した『和漢三才図会』というものです。
ここには「煮て、黒汁をとり去り、ぶた、鶏肉と一緒に再び似て食べる。味は佳い。」って書いてあります。
「黒汁」がキーワード。
ムクナ豆を水に浸したり、煮たりすると、黒い汁になります。ムクナ豆からLドーパという物質が出て墨汁を薄めたように黒くなるんですけど、ほかの豆類のほとんどは水に漬けていても黒くはなりません。
要するに
と紹介されてるわけ。
きっと江戸時代にはムクナ豆が栽培されていたのでしょう。

当時の人々の食卓にムクナ豆が並んでいたことを伺わせています。

八升豆は「1粒の種から八升(約14リットル)できる」という由来があるくらいなので、たくさん実をつけるムクナ豆は魅力的な豆だったはず。
江戸時代の人たちの大~事な食糧源だったんでしょうね♪
では、徐々に現代に近づいていきます。
日本で手に入りにくい理由
江戸時代になるとムクナ豆は食事に取り入れられました。
でも、なぜ日本人はムクナ豆を食べなくなったの???
実際のところはよく分かっていません。

まめ子の仮説としては―――
ムクナ豆は先ほど紹介した「黒い汁」が出ます。
ドーパミンが足りている人や胃腸が弱っているときに、ムクナ豆のLドーパを摂取しすぎてしまうとお腹を壊すことがあるようです。
ですので、料理に使うときは黒い汁を捨てないといけないのが面倒になったのかな。
ムクナ豆は水で戻さないと食べられません。だいたい一昼夜ぐらい水に浸しておきます。
面倒くさくなったのかな。
どっちにしても、「面倒だ」というイメージがついて、ムクナ豆は徐々につくられなくなったと考えています。
いろいろ調べていると、1970年代に発行された園芸の書籍にもムクナ豆を発見(#^.^#)
でも、「栽培が減少している」と書かれています。
この頃までは今以上に各地で育てられていたんでしょうね。
そして、時は流れて平成。
Lドーパの除草の効果が科学的に証明されます。
また、ムクナは比較的育てやすい植物だと分かり、いろんなところで注目されるようになりました。

そして、農業を営む方、私たち敷島屋のような存在が増えていき、ムクナ豆はインターネット販売を中心に少しずつ流通するようになったってわけです。
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
今回は3000年前から現代までのお話でした。
敷島屋の公式サイトでは、2021年に収穫したムクナ豆パウダーを販売中。
今日お伝えしたムクナ豆は私たち敷島屋の人気シリーズ。
熊本産のムクナ豆はパウダータイプ、錠剤タイプ、生タイプ取り揃えています。
公式LINEでお友達登録すればお得な情報やブログ情報もゲットできま~す。
最後までお読みいただきありがとうございました。
![]()
トップページへ